大石田町 高野一栄邸
|
| 7月14日・15日・16日 |
曾良日記 6月28日
馬借りて天童に趣く。六田にて、又内藏に逢う。立寄ってもてなしを受ける。
|
午後2時頃、大石田の一英(一栄)宅に着く。両日共に雨降りそうで降らず。上飯田(本飯田。現村山市内)より一里半。川水と出合う。其の夜、疲労により俳諧無く、休息す。
|
6月29日
夜に入り小雨降る。発句・一巡(各自一句ずつ詠み)終えて、翁(芭蕉)両人を誘い黒瀧(黒滝山向川寺)ヘ参詣。
予(曽良)は疲労の為辞退。午後2時頃にご帰宅。
道々、俳諧有り。夕飯は川水がもてなす。夜に入り一栄宅に帰る。 |
6月30日
朝方曇り、午前8時頃、晴れ。この日「さみだれを」歌仙成る。翁(芭蕉)其の辺を散策し、帰宅後に各句を清書し仕上げられる。
|
|
大石田
最上川のらんと、大石田と云所に日和を待つ。
|
| 最上川を舟で下ろうと、大石田というところで日和を待った。 |
爰(ここ)に古き誹諧の種こぼれて、忘れぬ花のむかしをしたひ、
|
ここには古くから俳諧の文化が伝えられ、今も昔の隆盛を忘れることができない
|
芦角一声(ろかくいっせい)の心をやはらげ、
|
葦笛(あしぶえ)の響きのような田舎じみた心を、俳諧が慰めてくれるので、
|
此道(このみち)にさぐりあしして、新古(しんこ)ふた道にふみまよふといへども
|
新しい句風がいいのか、古い句風が正しいのか迷っているところです。
|
道しるべする人しなければと、わりなき一巻(ひとまき)残(のこ)しぬ。
|
適当な指導者がいないから。頼まれても断りもできず、俳諧連句一巻を残した。
|
このたびの風流(ふうりゅう)、爰(ここ)に至れり。
|
| このようにして、ここに蕉風の種をまくようなことになった。 |
最上川
最上川は、みちのくより出て、山形を水上(みなかみ)とす。
|
| 最上川は、みちのくから流れでて、山形を上流とする川である。 |
碁点、隼など云う恐ろしい難所有
|
| 中流には、碁点や隼などという恐ろしい難所のある川である。 |
板敷山(いたじきやま)の北を流れ、果は酒田の海に入
|
| 歌枕で有名な板敷山の北を流れて、最後は酒田の海に入る。 |
左右山覆ひ、茂みの中に船を下(くだ)す。
|
| 川の左右の両岸から山が迫って、樹木の茂みの中を舟は、下って行く。 |
是(これ)に稲つみたるをや、いな船といふならし。
|
| この舟に稲を積んだのを、古歌に、稲舟(いなぶね)と詠んでいるようである。 |
白糸の滝は、青葉の隙々(ひまひま)に落て、仙人堂、岸に臨(のぞみ)て立
|
| 白糸の滝は青葉の木々の間に落ち、仙人堂は川岸に臨んで立っている。 |
水みなぎって舟あやうし。
|
水量が豊かで、何度も舟がひっくり返りそうな危ない場面があった。
|
五月雨を あつめて早し 最上川
|
西光寺(さいこうじ)
|
・場所:山形県北村山郡大石田町字大石田乙692 Yahoo!地図
|
・説明:
|
2013.5.23

|
|
西光寺(さいこうじ)
|
・場所:山形県北村山郡大石田町字大石田乙692 西光寺 Yahoo!地図
|
さみ堂礼遠 あつめてすゝし もかミ川
|
さみだれを あつめてはやし もがみがわ
|
・句意:降り続く五月雨を一つに集めたように、何とまあ最上川の流れの早くすさまじいことよ。
・詠んだ時期・場所:1689年 「奥の細道」
山形県大石田の船宿経営高野平左衛門(一栄)方にて行われた句会の冒頭の発句
|
1764−1772年(明和年中) 土地の俳人土屋只狂が芭蕉の真筆を模刻して 建立
|
2013.5.23

2013.5.23

|
|
| 西光寺(さいこうじ) |
・場所:山形県北村山郡大石田町字大石田乙692 Yahoo!地図
|
中央の句碑
|
松尾 芭蕉(まつお ばしょう)
|
さみ堂礼遠 あつめてすゝし もかミ川
|
| さみだれを あつめてすずし もがみがわ |
・句意:降り続く五月雨(梅雨の雨)を一つに集めたように、何とまあ最上川の流れの早くすさまじいことよ。
・詠んだ時期・場所:1689年 「奥の細道」
山形県大石田の船宿経営高野平左衛門(一栄)方にて行われた句会の冒頭の発句
|
| 1975年(昭和50年) 建立 |
| 左:田中李兮の句碑 |
| ・説明: |
吹るゝや 骨となっても 枯尾華
|
| 1785年(天明5年)岡村好和の発意により暁花園社中 建立 |
右:暁花園の句碑 土屋只狂
|
| ・説明:−1789年 |
夜着重し 桜や咲ん 雨の音
|
1789年(寛政元年)暁花園社中(市馬窓社中) 建立
|
中央/松尾芭蕉 2013.5.23

2013.5.23

|
|
| 高野一栄邸跡(芭蕉3泊した所) |
| ・場所:山形県北村山郡大石田町本町 高野一栄邸跡 Yahoo!地図 |
| 芭蕉翁真蹟歌仙“さみだれを”の碑 |
松尾 芭蕉(まつお ばしょう)
|
さみだれを あつめてすゞし もかミ川
|
さみだれを あつめてすずし もがみがわ
|
・句意:降り続く五月雨(梅雨の雨)を一つに集めたように、何とまあ最上川の流れの早くすさまじいことよ。
・詠んだ時期・場所:1689年 「奥の細道」
山形県大石田の船宿経営 高野平左衛門(一栄)方にて行われた句会の冒頭の発句
|
1989年(平成元年) 建立
|
高野 一栄(たかの いちえい)
|
・説明: − 年 大石田村の河港近くの船問屋 本名:高野平右衛門:平四郎
高野一栄邸跡(芭蕉3泊した所) |
岸にほたるを 繋ぐ舟杭
|
句意:
歌仙の脇句
|
河合 曽良(かわい そら)
|
・説明:1649−1710年 長野県諏訪市生まれ 俳諧師 芭蕉の奥の細道に同行した弟子
蕉門十哲の一人 |
爪ばたけ いざよふ空に 影待ちて
|
句意:
|
高桑 川水(たかくわ せんすい)
|
・説明:−1709年 67歳 高桑加助吉直、金蔵と称し、大石田の庄屋(村長)を勤めた、のちに隠居して加助と称した。同家の過去帳によれば、大石田高桑家はもと下野国芳賀郡の出で、尾花沢の銀山が隆盛の頃に、大石田に移り住んだ。川水は、その三代目金蔵重好の長男として生まれたが、四代目は末弟の宗左衛門吉武が継いだようである。「おくのほそ道」当時、川水は隠居の身
|
| 里をむかひに 桑のほそミち |
句意:
|
高橋 一栄(たかの いちえい)
|
・説明: − 年 大石田村の河港近くの船問屋 本名:高野平右衛門:平四郎
高野一栄邸跡(芭蕉3泊した所) |
| うしのこに こゝろなくさむゆふまく |
句意:
|
松尾 芭蕉(まつお ばしょう)
|
・説明:1644−1694年 51歳 三重県伊賀市出身 本名:松尾宗房(まつおむねふさ)
江戸時代前期の日本史上最高の俳諧師の一人 |
水雲重し ふところの吟
|
句意:
|
高野一栄 邸跡 2013.5.23

芭蕉翁真跡歌仙“さざなみを”句碑


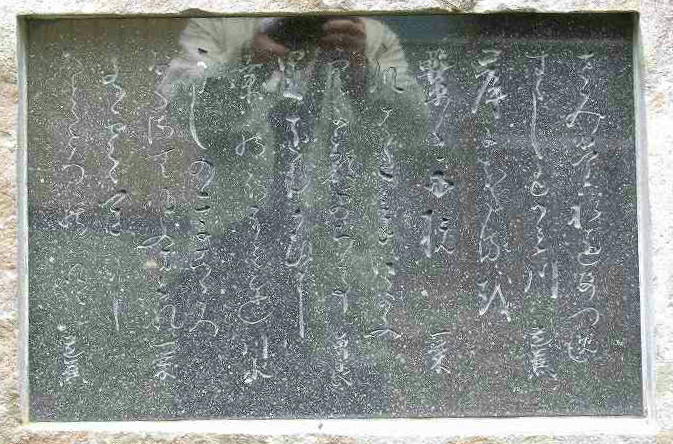
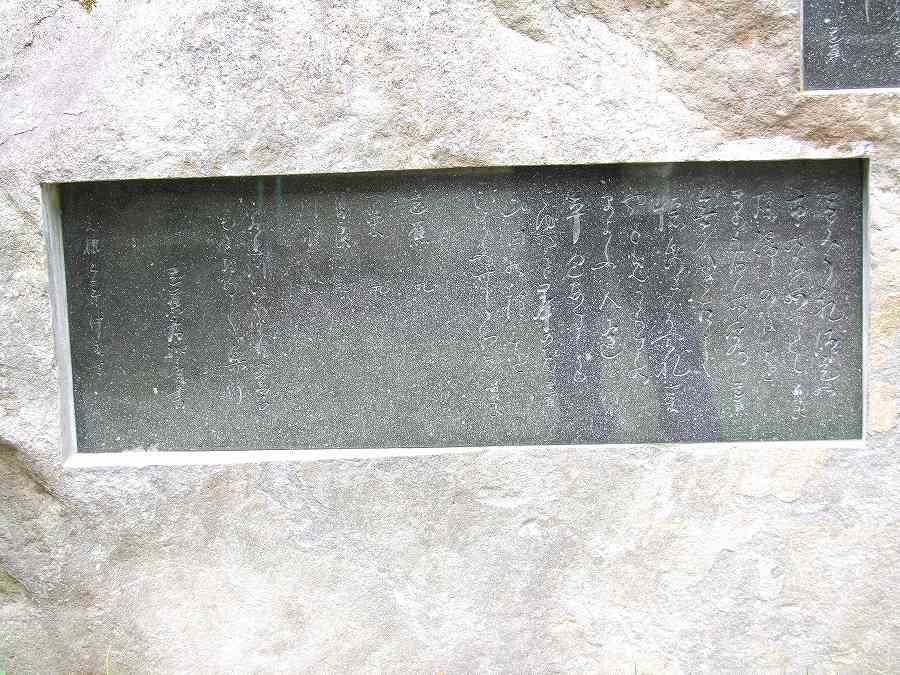
|
|
舟形町へ
|