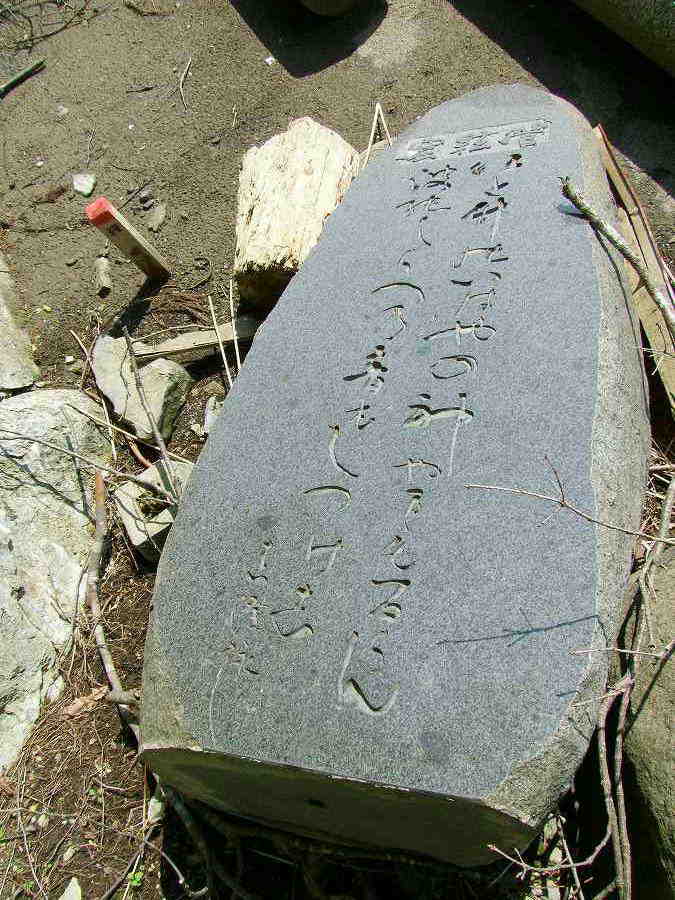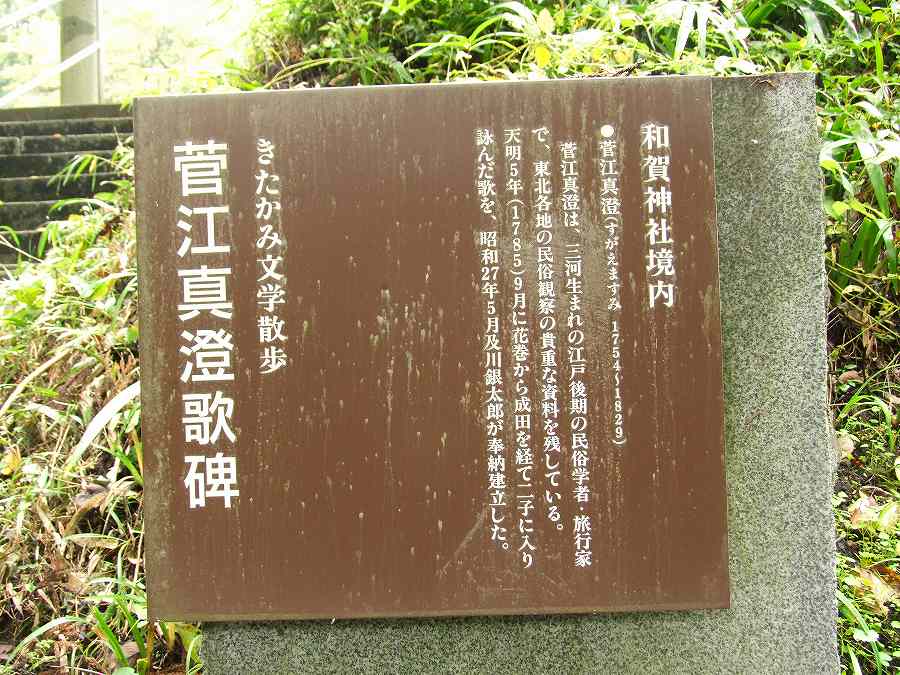| 菅江 真澄(すがえ ますみ) |
・説明:1754−1829年 76歳没 愛知県豊橋生まれ 江戸時代後期の紀行家・民俗学者
30歳で旅立ち、長野から新潟、山形、秋田、青森、北海道、岩手、宮城、福島を巡り、
48歳で再び秋田に入り、角館で亡くなるまで延べ29年間を秋田で過ごした。 |
・宮城県関連
1786年(33歳)6〜9月:大原(岩手県大東町)から気仙沼(7月8日〜8月4日滞在)大島
松島・塩竈神社・多賀城跡を見る。「月の松島」8月15日
1986年12月3日以降の日記が見つからず細部不明だそうです。
1786〜1787年:「雪の松島」確定できず
1787年:仙台・松島などを巡る。
1788年:松島で桜を見る。「花の松島」3月下旬
6月に前沢から松前へ
|
| 神明崎(みょうじんざき) 管弦窟 |
| ・場所:宮城県気仙沼市魚町二丁目6 神明崎 Yahoo!地図 |
| 菅江 真澄(すがえ ますみ) |
いと竹の いはやの神や まもるらん 波のしらべの 音もしづけし
|
歌意:
いとは糸で弦、竹は管、管弦窟の神様が守ってくれるので波も音も静かだ
|
1978年(昭和53年) 建立
|
2006.7.31

3.11津波被害 2012.5.19
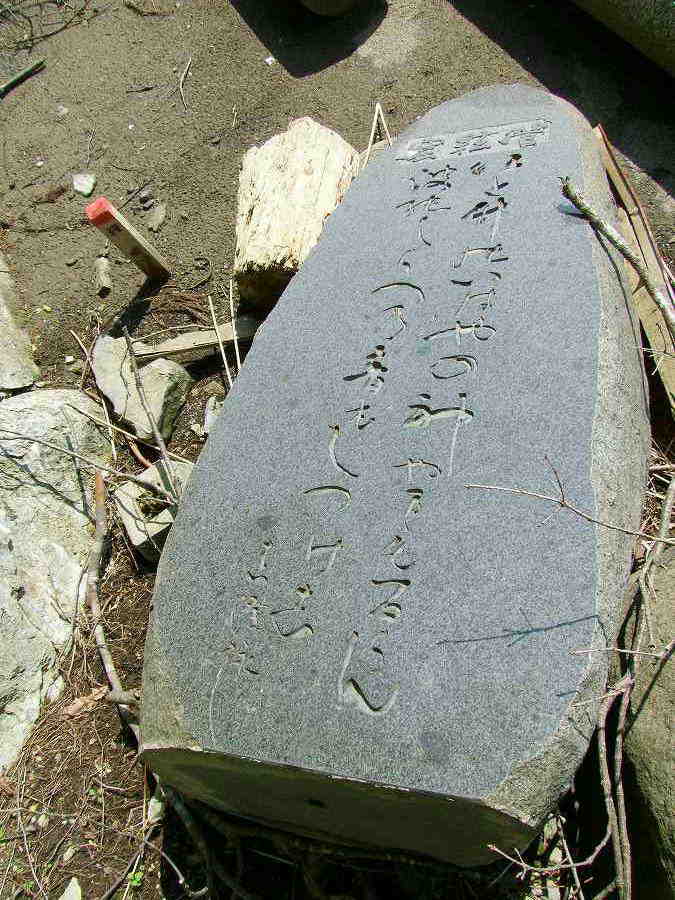
|
|
観音寺
|
| ・場所:宮城県気仙沼市本町1-4-16観音寺境内 Yahoo!地図 |
| 菅江 真澄(すがえ ますみ) |
萩すすき 手向の草の それたにも つゆけき増る 秋の山寺
|
歌意:
|
年 建立
|
2012.5.19

|
|
和賀神社
|
| ・場所:岩手県北上市二子町坊舘 和賀神社 Yahoo!地図 |
| 菅江 真澄(すがえ ますみ) |
冬ちかみ あらしの風も はやちねの 山のかなたや 時雨そめけむ
|
歌意:
1785年(天明5年)9月 花巻から成田を経て二子に入り詠んだ歌
|
1952年(昭和27年) 及川銀太郎 建立
|
2013.10.23
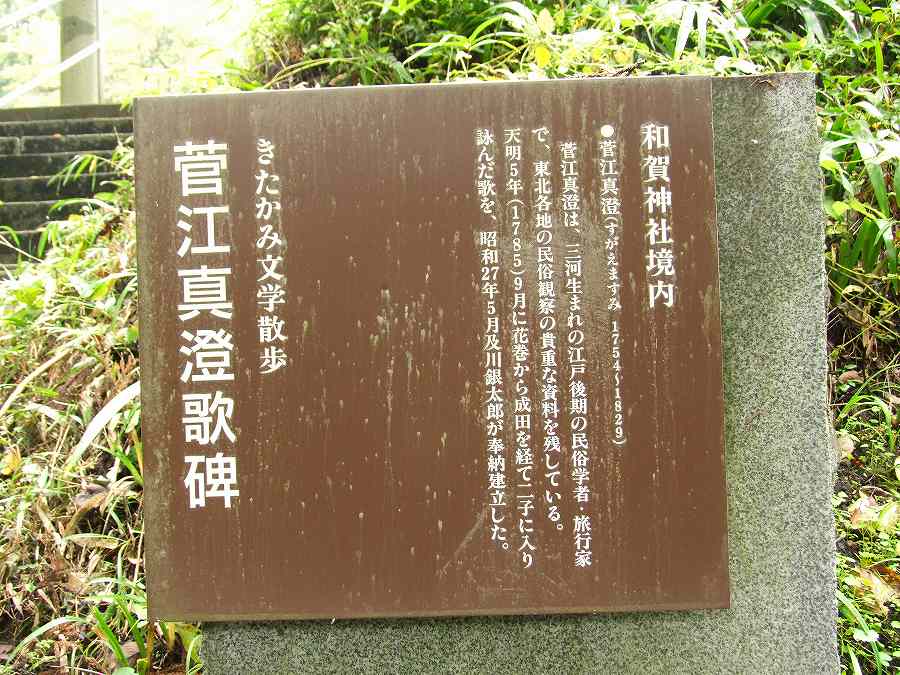
2013.10.23

裏 2013.10.23

|
|
忠功寺
|
| ・場所:岩手県奥州市胆沢区小山焼山77 Yahoo地図 |
| 菅江 真澄(すがえ ますみ) |
遠ざかる 日数ももゝの 花かづら かけてやよひの 空に手向む
|
歌意:
1786年 忠功寺の僧侶の百か日法要が営まれると聞き詠んだ和歌 |
年 建立
|
2014.7.30

|
|
霊桃寺(れいとうじ)
|
・場所:岩手県奥州市前沢区字山下72 Yahoo地図
|
| 菅江 真澄(すがえ ますみ) |
天明6年3月15日夜
今宵は霊桃寺の御寺ていねたり 16日曙を見ようと
障子開けたければ いと高き処にて、残る かたなふ見やられたり
|
束稲(たばしね)の 花の昔や いかならん 嶺もふもとも かすむあけぼの
|
歌意:
天明6年:1786年
|
2009年(平成21年) 現住 正勝 建立
|
2014.7.30

|
霊桃寺(れいとうじ)
|
・場所:奥州市前沢区字山下72 Yahoo地図
|
| 菅江 真澄(すがえ ますみ) |
天明6年4月9日 菅江真澄 読む
前 霊桃寺
|
詩意:
|
2009年(平成21年) 現住 正勝 建立 菅江真澄直筆
|
2014.7.30

|
|
鎮岡神社(しづめがおかじんじゃ)
|
・場所:岩手県奥州市江刺区岩谷堂五位塚179 参道階段
|
菅江 真澄(えざき ますみ)
|
かしこしな あらふるとても ぬさとらは こころしつぬの 岡の神籠
|
| 句意: |
年 建立
1785年(天明5年)訪れて詠む
|
|
|
国見極楽寺
|
・場所:岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町62 Yahoo地図
|
陸奥胆沢郡須輪神社法楽八景和歌
片岡夕照(江刺郡片岡村)
|
| 菅江 真澄(すがえ ますみ) |
又や見ん 片岡山の 夕日影 花や紅葉の いろならねとも
|
| 歌意: |
| 1982年(昭和57年) 建立 |
|
|
善知鳥神社(うとうじんじゃ)
|
| ・場所:青森県青森市安方2-7-18 Yahoo地図 |
菅江 真澄(すがえ ますみ)
|
長閑しな外か浜 風鳥すらも世は 安潟とうとふ声して
うちなびく たむけのぬさも ふりはへて かうかうしくも みゆるみづ垣
|
| 歌意: |
1957(昭和32年)建立
|
| |
菅江真澄 説明碑
|
愛知県(旧三河国)豊橋に生れる。姓は白井、幼名は英二といい、青年に達して秀夫。菅江真澄と称したのは、晩年、秋田に居住してからである。
最初の天明5年(1785)8月のときは、蝦夷地(現・北海道)へ渡るためであった。大飢饉による餓死者の無残な姿を見て、これ以上浜路をめぐることは、自らも飢える心配があると考えて引き返した。
二度目の来青は、天明8年(1788)7月である。浅虫を経て青森、三厩から蝦夷地へわたった。この時烏頭(うとう)神社に詣でた後、古い社の後が残っているということから、二本木のある丘(現・久須志神社)を訪ねている。
また、この杜を見て「青森という地名もここがもとであろう」と「外ケ浜づたひ」に記録している。
三度目は、寛政8年(1798)で二十余日滞在、青森の各集落、社寺、山野等を歩きまわり、伝承習俗や庶民の生活を「すみかの山」に詳しく記録している。
なかでも注目されることは、4月14日、石神村の小さな祠のかたわらに、「文永の碑があった」と記録していることである。
|
・年(年)建立
|
|
|
杉沢 熊野神社
|
| ・場所:秋田県能代市盤字杉沢 |
| 菅江 真澄(すがえ ますみ) |
| たづねても 三輪の山 もとそれならで ここにいく世を 杉沢の碑 |
| 歌意: |
|
|
粕毛字下根城
|
・場所:秋田県藤里町粕毛字下根城
|
| 菅江 真澄(すがえ ますみ) |
山影に 佃るよね田に 風落ちて 涼しく渡る 川添ひの道
|
| 歌意: |
| 年 建立 |
|
|
| |
象潟を詠んだ歌
|
| 菅江 真澄(すがえ ますみ) |
秋田のかりね
|
なみ遠く うかれてここに きさかたや かつ袖ぬるる 夕ぐれの空
|
歌意:
|
|