仙台市野草園
|
| 仙台市野草園 |
・場所:宮城県仙台市太白区茂ヶ崎2−1−1 Yahoo!地図
|
スズキ ヘキ/鈴木 碧(すずき へき)
|
説明:1899〜1973年 本名:鈴木栄吉
終生仙台をはなれず「みやぎの子どもにはみやぎのうたを」と自ら原始童子になりきって童謡つくりに情熱をもやし続けた。日本稀有の天稟童謡作家である。
雑誌「赤い鳥」の影響を受けた |
| ツクシンボコヤマ |
ツクシンボコヤマ ネムイネムイ コヤマ
オジョーサンノ オバシャガ オヒルニ トール
オバシャノ ギョシャガ ネムガッテ コマル
オバシャノ ウマモ ネムガッテ コマル
ネムイ ネムイ コヤマ ツクシンボ コヤマ |
2014.9.7
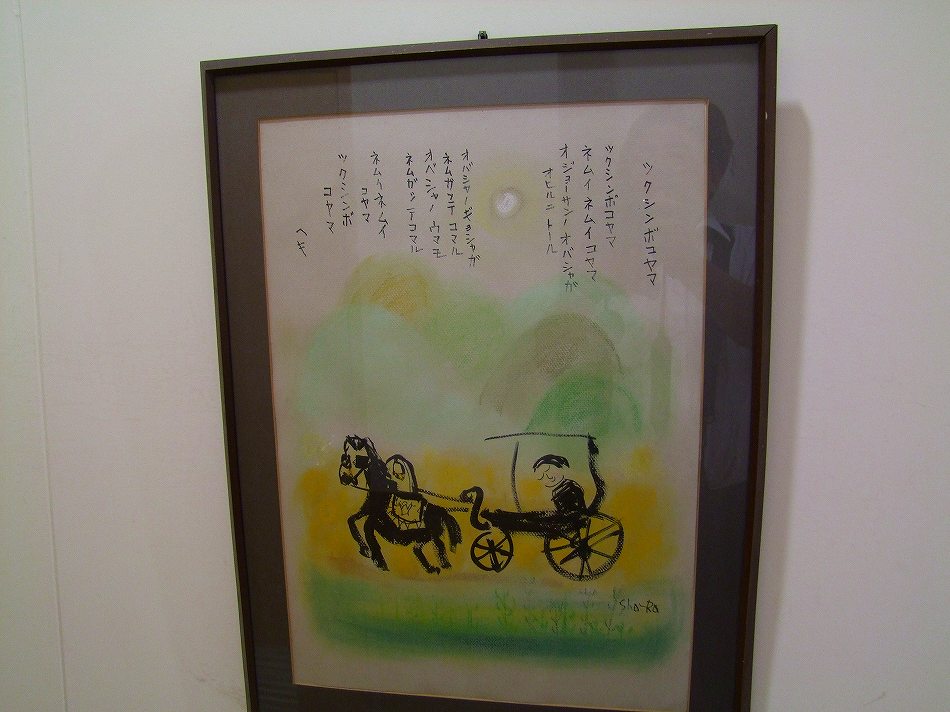
2014.9.7
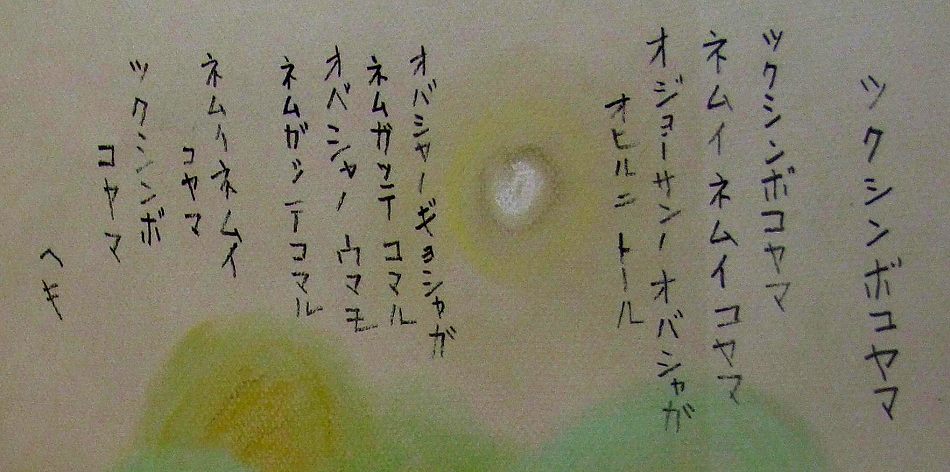
|
|
| スズキ ヘキ/鈴木 碧(すずき へき) |
| 左萩の道。どんぐり山 |
ユクヒトハ ハギノモン アキノボウシト アキノクツ
|
1983年(昭和58年) 開園20周年を記念 建立
|
2012.3.22

|
ハギノトンネル コモレビハ アカク チラバル
|
2012.3.22

|
|
スズキ ヘキ/鈴木 碧(すずき へき)
|
・説明:1899?1973年 本名:鈴木栄吉
終生仙台をはなれず「みやぎの子どもにはみやぎのうたを」と自ら原始童子になりきって童謡つくりに情熱をもやし続けた。日本稀有の天稟童謡作家である。
雑誌「赤い鳥」の影響を受けた |
| 野草園野外卓詩 |
コガラシ コボウズ ハセテイル
ドンドン オヤマヲ ハセテイル
|
1983年(昭和58年)開園20周年を記念 建立
|
2014.9.7

|
コドモガ ユクヒニャ サムイヒニャ
コガラシ コボウズ ヒロッテル
|
2014.9.7

|
サムクテ コドモハ ユカレナイ ドングリ ヒロイニ ユカレナイ
ドンドン オヤマヲ ハセテイル ドングリ コロガシ ハセテイル
|
2014.9.7
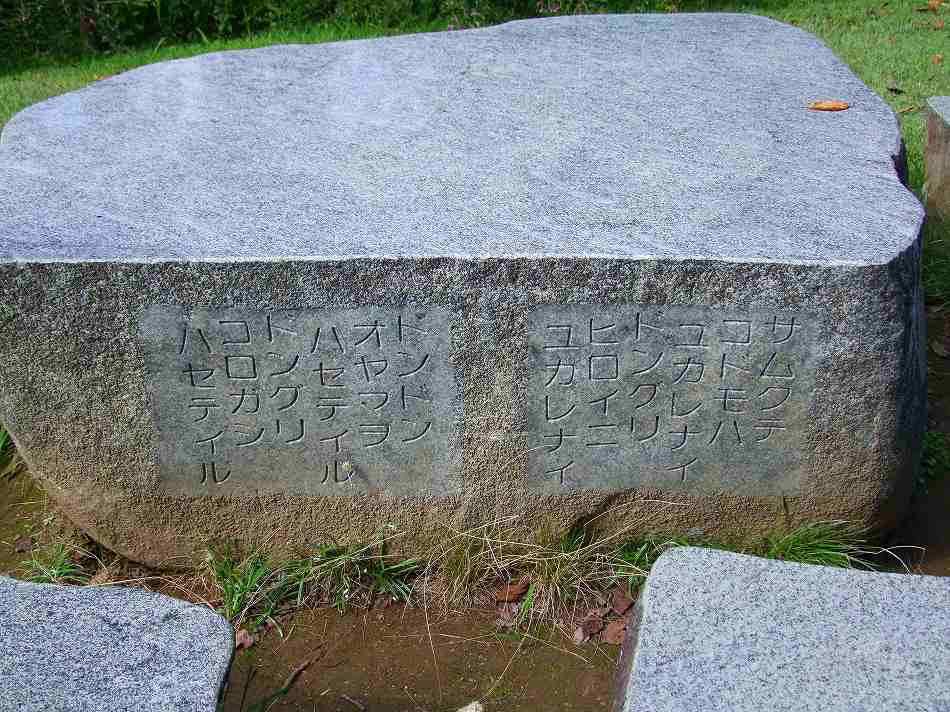
|
|
菅野 邦夫(かんの くにお)
|
・説明:1929−年 宮城県亘理町生まれ 宮城県農学校園芸学専攻科卒
1950年より仙台市野草園造成に参加
元仙台野草園長 1990年退職 シロバナミヤギノハギ発見者
|
や
さ
し
い
花
へ
|
萩
咲
く
里
の
|
萩
茶
を
わ
か
し
|
ゆはぎを
つくり
|
花見に
おいで
|
萩
の
花
咲
い
た
|
か
ん
の
邦
夫
|
萩
の
里
|

|
意:
|
や
さ
し
い
花
に
|
萩
咲
く
星
の
|
し
ら
つ
ゆ
光
る
|
か
ざ
し
の
花
に
|
か
ざ
し
に
し
よ
う
|
萩
の
花
咲
い
た
|
2015.5.8

|
1998年(平成10年)仙台エコーライオンズクラブ創立35周年記念
|

|
|
蓬田 紀枝子(よもぎた きえこ)
|
・説明:1930−年 仙台市生まれ 阿部みどり女に師事。平成6年〜16年「駒草」を継承主宰。
評伝「俳人阿部みどり女ノート」で1994年度(平成12年度)俳人協会評論賞
|
はんてんぼく いまは芽吹きの 大樹かな
|
句意:
|
年
|
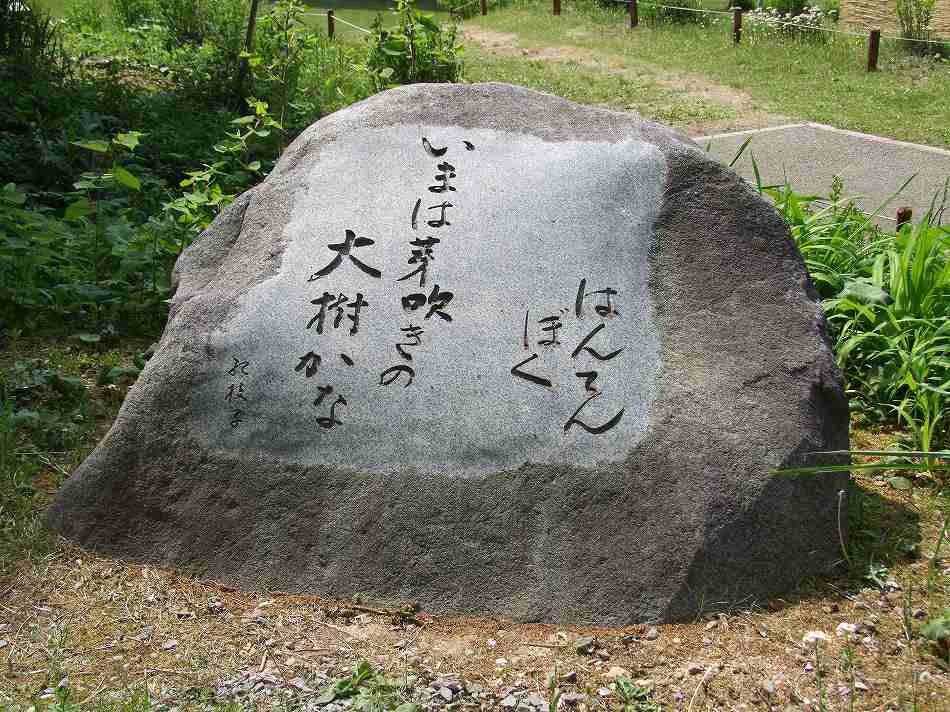
|
|
いではく:作詞
井出 博正(いで ひろまさ)
|
・説明:1941−年 長野県 本名・井出 博正(いで ひろまさ)作詞家 早稲田大学卒
|
北国の春
白樺 青空 南風 コブシ咲くあの丘北国の ああ北国の春
季節は都会では わからないだろうと 届いたおふくろの
小さな包み あの古里に帰えろうかな 帰えろかな
|
作曲:遠藤 実 歌:千 昌夫 1977年発売
|
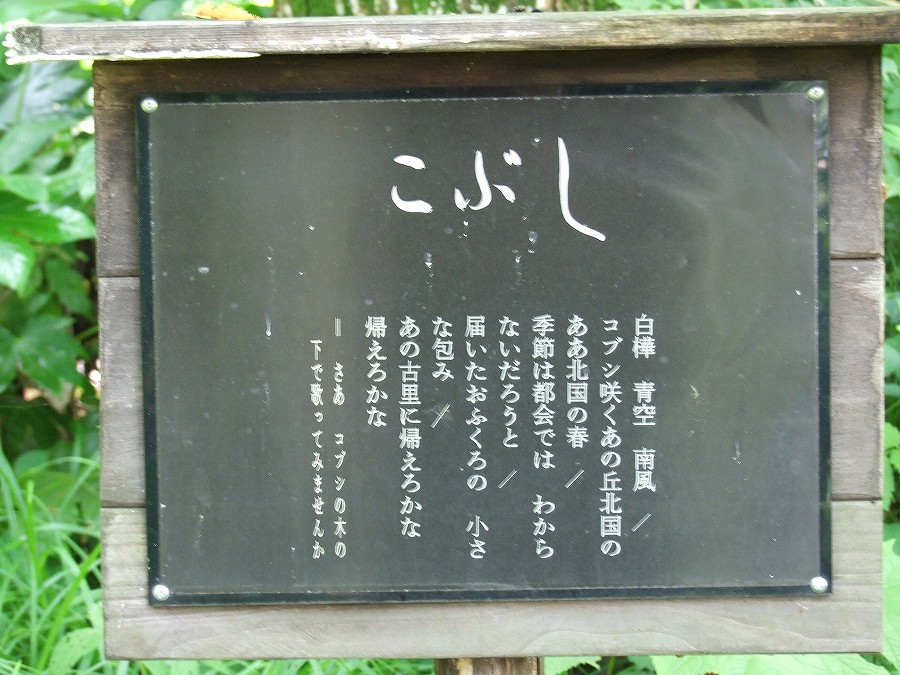
|
|
阿部 みどり女(あべ みどりじょ)
|
・説明:1886−1980年 札幌生まれ 札幌北星女学校修了 俳人
父は第2代北海道庁長官 第7師団長 永山武四郎の四女 本名:ミツ
長谷川かな女・杉田久女とともに、女流俳句草創期を代表する一人
1910年:阿部卓爾と結婚して東京に住むが、結核のため鎌倉で療養 俳句を始める。
1915年:高浜虚子に師事
1929年:「ホトトギス」を中心に作品を発表
1931年:河北新報の俳壇の選者となる
1944年(昭和19年):長女の婿(一力五郎 河北新報社三代社長)の勧めで仙台市に疎開し
定住 仙台には1978年(昭和53年)まで生活
弟子:蓬田紀枝子、寺島ただし
|
桔梗の 蕾をぽんと 鳴らしけり
|
2023.5.14
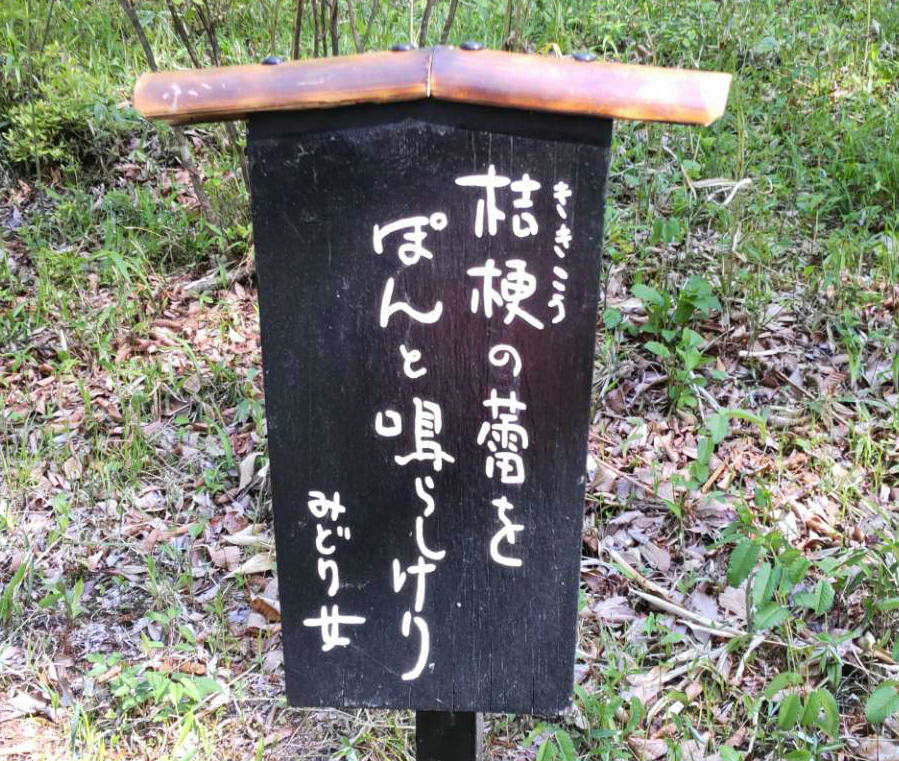
|
|
展示ケース 作者不明
|
萩の雨 篠笛の音の のびやかに
|
| 妻と来て まずは一服と 萩のお茶 いただきて巡る 秋の野草園 |
| 短冊を 読んでは巡る 萩の丘 |
2023.5.14
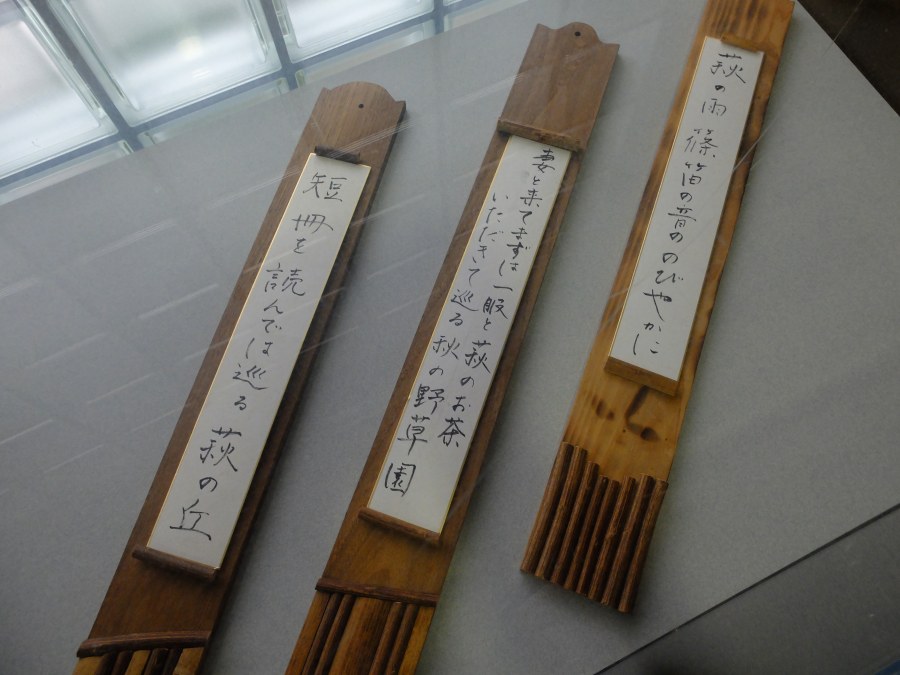
|
|
阿部 みどり女(あべ みどりじょ)
|
・説明:1886−1986年 札幌生まれ 札幌北星女学校修了 俳人
父は第2代北海道庁長官 第7師団長 永山武四郎の四女 本名:ミツ
長谷川かな女・杉田久女とともに、女流俳句草創期を代表する一人
1910年:阿部卓爾と結婚して東京に住むが、結核のため鎌倉で療養 俳句を始める。
1915年:高浜虚子に師事
1929年:「ホトトギス」を中心に作品を発表
1931年:河北新報の俳壇の選者となる
1944年(昭和19年):長女の婿(一力五郎 河北新報社三代社長)の勧めで仙台市に疎開し
定住 仙台には1978年(昭和53年)まで生活 弟子:蓬田紀枝子、寺島ただし
|
重陽の 夕焼けに逢ふ 幾たりか
|
| ちょうようの ゆうやけにあふ いくたりか |
句意:目の前の見事な夕焼け この素晴らしい夕焼けに出会ったのは幾人だろうか。
|
2023.9.29
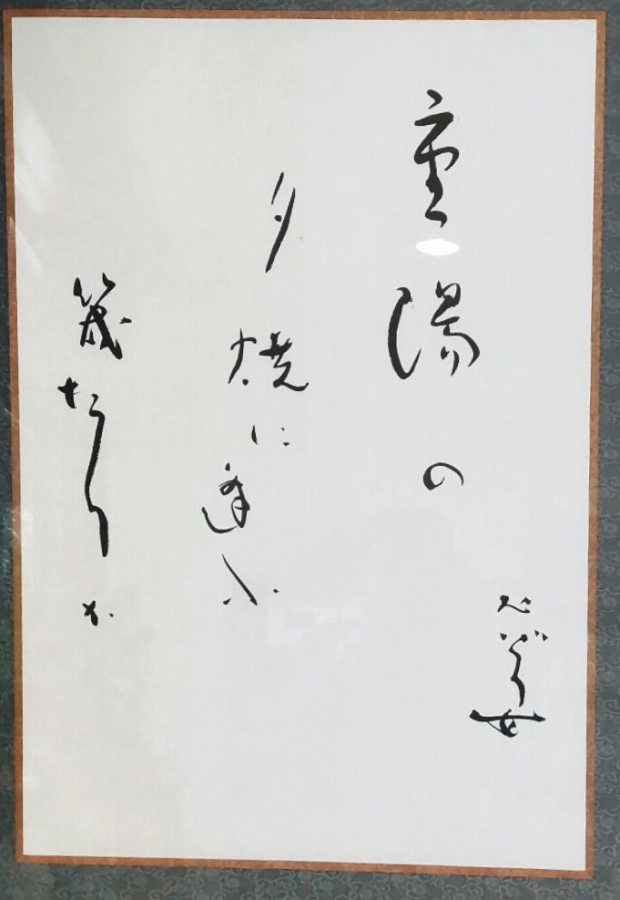
|
|
|