| 市原 多代女(いちはら たよじょ・たよめ) |
・説明:1776−1865年 90歳没 須賀川豪商市原家に生まれ 本名:多代女(たよめ)
江戸時代の代表的名女流俳人
俳諧を石井雨考に学ぶ。鈴木道彦に入門。松窓乙二に師事する。晴霞庵と称した
松尾芭蕉を尊敬「奥の細道」で須賀川をおとずれた松尾芭蕉の句碑建立
|
瑞巌寺(ずいがんじ)
|
| ・場所:宮城県宮城郡松島町松島 瑞巌寺境内 Yahoo!地図 |
須賀川の多代女
|
| こゝろやゝ まとめて月の 千松島 |
裏碑には12人の俳句が刻まれている。
|
時期・場所:奥の細道出発前
|
1851年(嘉永4年) 大阪の鼎左、江戸の一具ら 建立
|
真ん中の碑 2010.3.5

真ん中の碑 2010.3.5

2013.7.2
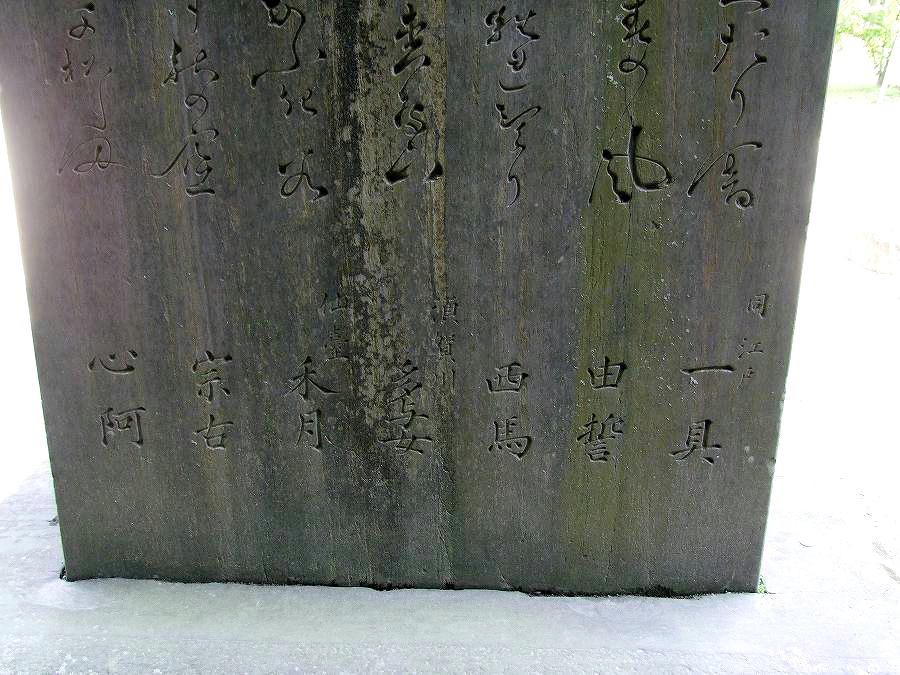
|
|
十念寺(じゅうねんじ)
|
| ・場所:福島県須賀川市池上町101番地 Yahoo地図 |
市原 多代女 辞世の句
|
終(つい)に行く 道はいづくぞ 花の雲
|
| 句意: |
年(年) 建立
|
2013.12.7

2013.12.7

|
十念寺(じゅうねんじ)松尾芭蕉句碑
|
| 市原 多代女 |
風流の はしめや奥の 田うえ唄
|
句意:芭蕉が須賀川を訪れたときに詠んだ歌 たよ女80歳
|
1855年(安政2年) 市原多代女 建立
|
2013.12.7

|
|
神炊館神社
|
| ・場所:福島県須賀川市諏訪町 |
石井雨考と市原多代女の直筆の句碑
|
| 石井 雨考(いしい うこう) |
鶴亀も 下戸にはあらじ 膳飛羅起(ひらき)
|
句意:商人のお祭りであった恵比須講の情景を詠んだもの
|
| 市原 多代女(いちはら たよじょ) |
此うえに 又としよらん 初時雨
|
句意:
81歳の書 |
2013年 両俳人の子孫である、 石井敬三氏(諏訪町)と市原良彦氏(栄町)が同神社に寄贈 建立
|
|
|
文部省唱歌「藤の花」
|
藤の花
一、野山もかすむ春雨の 霽(は)れて、なごりの
「水嵩(みずかさに)に 車はげしや 藤の花」(市原多代女の句)
しぶきに濡れて日に映ゆる。
二、雲雀の声は夕空に 消えて、此方(こなた)の
「薮畠や穂麦にとどく藤の花。」(宮崎荊口の句)
しづかに揺れて日は暮るる。
|
句意:水車は水が増して勢よく回っている。そこには藤の花が咲いている。
|
|
| 宮の辻(みやのつじ)ポケットパーク |
| ・場所:福島県須賀川市宮先町 Yahoo地図
市原多代女の生家のあった所 |
めかくしを とればひゝなの 笑顔かな
|
句意:
|
年 須賀川商工会議所婦人会 建立
|
|
|
| |